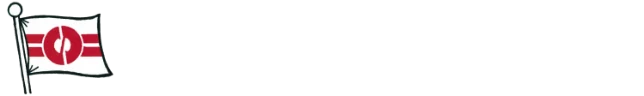二見港


二見港は佐渡ヶ島の西南部、真野湾の西北部に位置し、東は小佐渡山脈にいだかれ、西は台ヶ鼻燈台をもち、船舶の安全性を確保している。荒天の場合は越佐間はもちろん、遠く北海道、九州航路の船舶の安全性を確保している。波浪は、春夏、0~1.5メートル、秋冬0~2メートルであり、いづれも南西の方向である。おもなる出入貨物は、金属および同製品、木材類、セメントなどである。物揚場としえ144メートル、ひき場として134メートルの施設がある。新潟県唯一の避難港である。P.253
『概観 佐渡』 佐渡郡教育研究会編集 両津市教育研究会 概観佐渡刊行委員会 発行
昭和39年6月
二見(ふたみ)



二見半島の東岸、真野湾側の集落。元村と新地に分れる。永徳元年(一三八一)の本間道喜申状ならびに足利義満(カ)の袖判安堵状写によると、道喜が「蓋見半分」の地頭職を安堵されている(本田寺文書)。戦国期には、沢根本間氏の領有。二見は、半島尖端の双股岩に由来するが、古来より真野湾側は湊として利用され、鶴子銀山時代は、沢根本間氏の湊であった。元禄検地帳は保存されていない。寛政元年(一七八九)「道中案内帳」には、村高一一六石余、田畑反別一二町八反、中宮大明神(二見神社)、真言宗龍吟寺、家数四四軒、人別一六四人とある。中世の湊は龍吟寺前の大泊で、近世には元村に移り、「佐渡雑志」(文政年間)に、「船掛り澗、深サ五尋余、但、西風ハ大風ニテモ当ラズ、東風ノミ悪シ、甚ダ能キ澗ナリ」とある。東風を待って上方に向う回船の湊であった。段丘上の「のさん」にあった光蓮坊は、龍吟寺の前身と伝えられるが、重要文化財の同寺の金銅聖観音は、双股岩近くにあがったと伝える。中世に、各地から寄り集って成立した湊集落。元村の阿弥陀堂には、沖合いの阿弥陀礁から上った一石表裏地蔵坐像があり、近くに「八房の梅」・「月見ずの池」などの順徳院伝説もある。寛永五年(一六二八)、相川の補助港となり、相川から稜線ぞいの旧道があった。近世、元村には十数軒の遊廓があり、のち明治四年、旧大泊地域を埋め立て新地と称し、ここに新しい町屋を建てた。
【関連】 二見港(ふたみこう)
【参考文献】 『佐渡相川の歴史』(資料集五)
【執筆者】 佐藤利夫
(『佐渡相川の歴史』別冊 佐渡相川郷土史事典より引用)